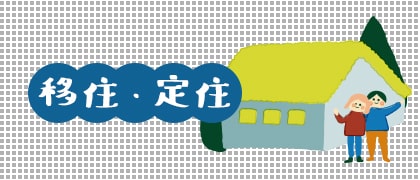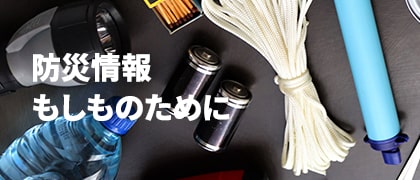木造薬師如来坐像 1軀
| 指定区分 | 国指定重要文化財 |
|---|---|
| 所蔵 | 福満寺 |
| 時代 | 藤原時代末 |
| 像高・寸法 | 像高 147cm 総高 387.9cm |
| 材質・形状 | 桂材 寄木造 素地 |
| 住所 | 399-7702 長野県東筑摩郡麻績村山寺 |
薬師如来は、薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)とも呼ばれ人間の病をいやし、心の苦悩も取除くなど十二の誓願をたてた如来で、仏教伝来の初期から盛んに造像され、信仰されてきた仏である。
福満寺の薬師如来は、その大きさが東日本随一と言われており、豊かに張った両頬、両眼を切れ長に刻み眼尻まで見ひらいた顔立ちは中々に雄偉の相である。
右手は、施無畏印(せむいいん)といって人々の病気や心配事などあらゆる苦しみを取除く徳を施す印相(いんそう)を示し。
左手は、与願印(よがんいん)と言って人々に慈悲を施す印相とその掌の上に薬壺(やくこ)を乗せている。病に応じてこの薬を施し苦しみを除く薬師如来の誓願を表す。
かつて、この薬師如来は五十年に一度のお開帳の外は秘仏として人の目に触れることはなく、この仏を盗み見た者は目が潰れると言われてきた。
昭和二十二年仏体の修理を終え、お開帳を行い、それ以降大晦日の二年参りと、五月三日の縁日には拝観できることとなった。
福満寺について
「井掘薬師如来縁起」によれば、嘉祥(かしょう)二年(八四九)円覚大師円仁東国巡化の折、当地に入り道に迷われたるに、どこからともなく紫雲たなびき、霊光あらわれて進路を示され進み行くに、山腹に原野あり、一本の巨木横たわりたり、大師そこでこの霊木より薬師尊・日光・月光菩薩・四天王・十二神将を造り、一字を建立して、「我いま、仏勅(ぶっちょく)を奉じて薬師如来を安置し奉る、日々に鎮護国家・五穀豊穣・除災招福の秘法を修して霊験利生(れいげんりしょう)を得せしめよ」と申され、尚あまねく信者に福満無量ならんことを願われて、福満寺と名づけられた。と創建の由来を述べている。
創建当時は、現在地の北方1.5kmほど登った聖山の中腹、今そこを「寺所(てらどころ)」と呼んでいる場所に、壮大な本堂を中心にして南方一里(4km)東・西一里と伝える広大な寺域に七堂伽藍が整い、東谷(ひがしだに)六房・西谷(にしだに)六房甍(いらか)を競い、天台修験の道場として全盛を極めたといわれるが、今は蓮池(はすいけ)・鐘つき堂・坊平(ぼうだいら)・東大門・西大門・半在家(はんざいけ)・十王堂などの地名にその名を止(とど)めている。
寺が現在の場所に移ったのは、元禄元年(一六八八)と伝えられ、理由は山崩れによるとも、自然衰微によるとも言われるが、これに関する資料を欠き判然としない。
この記事へのお問い合わせ
教育委員会
長野県東筑摩郡麻績村麻3836 麻績村地域交流センター
- 電話番号
- 0263-67-4858
- Fax番号
- 0263-67-1023
- メール
- omi-kyoi@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。